
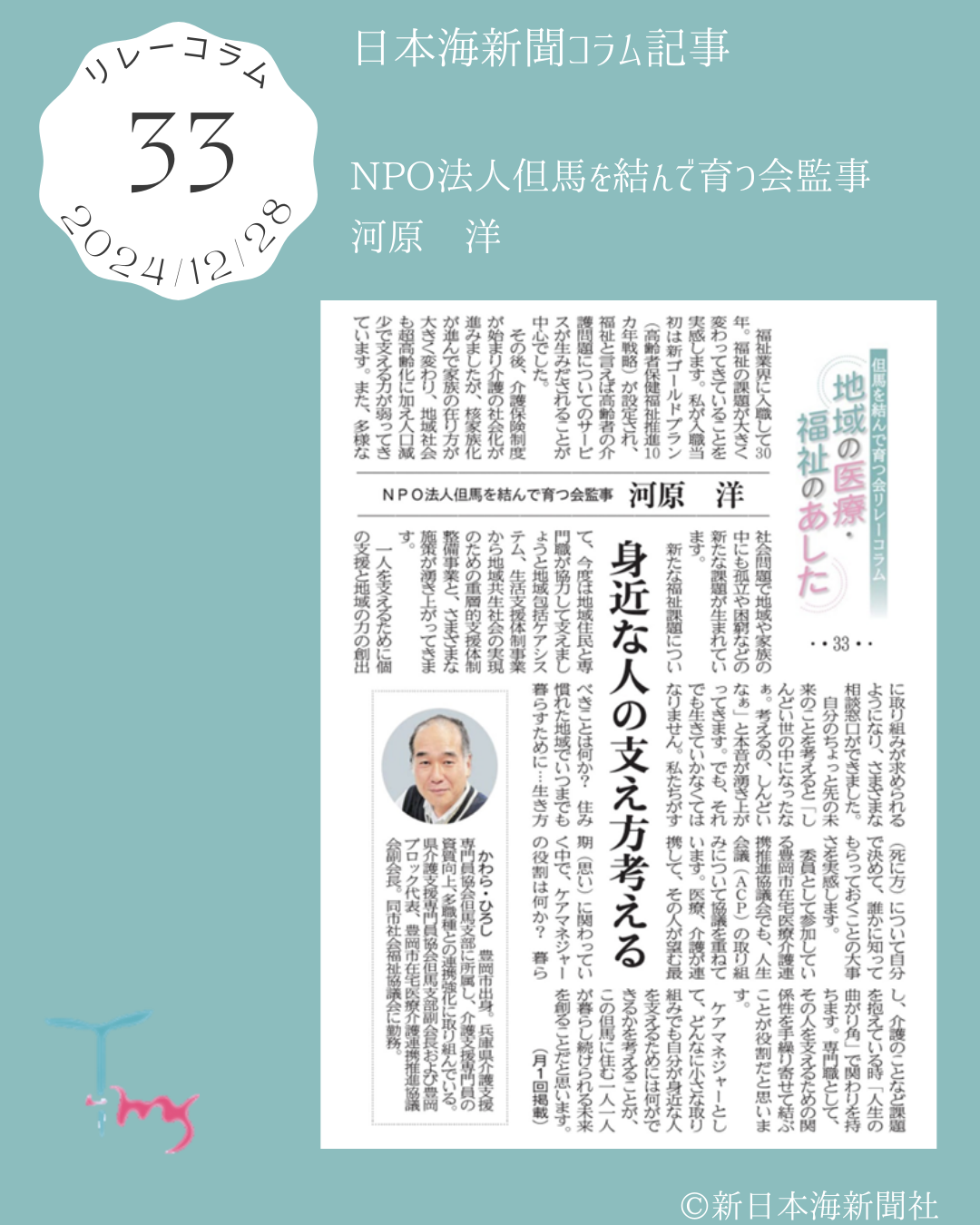
令和4年より、日本海新聞紙に‟但馬を結んで育つ会リレーコラム~地域の医療・福祉のあした~”が掲載されております。
令和6年12月は河原洋監事の寄稿です。
『身近な人の支え方考える』
福祉業界に入職して30年。福祉の課題が大きく変わってきていることを実感します。私が入職当初は新ゴールドプラン(高齢者保健福祉推進10カ年戦略)が設定され、福祉と言えば高齢者の介護問題についてのサービスが生みだされることが中心でした。
その後、介護保険制度が始まり介護の社会化が進みましたが、核家族化が進んで家族の在り方が大きく変わり、地域社会も超高齢化に加え人口減少で支える力が弱ってきています。また、多様な社会問題で地域や家族の中にも孤立や困窮などの新たな課題が生まれています。
新たな福祉課題について、今度は地域住民と専門職が協力して支えましょうと地域包括ケアシステム、生活支援体制事業から地域共生社会の実現のための重層的支援体制整備事業と、さまざまな施策が湧き上がってきます。
一人を支えるために個の支援と地域の力の創出に取り組みが求められるようになり、さまざまな相談窓口ができました。
自分のちょっと先の未来のことを考えると「しんどい世の中になったなぁ。考えるの、しんどいなぁ」と本音が湧き上がってきます。でも、それでも生きていかなくてはなりません。私たちがすべきことは何か?住み慣れた地域でいつまでも暮らすために…生き方(死に方)について自分で決めて、誰かに知ってもらっておくことの大事さを実感します。
委員として参加している豊岡市在宅医療介護連携推進協議会でも、人生会議(ACP)の取り組みについて協議を重ねています。医療、介護が連携して、その人が望む最期(思い)に関わっていく中で、ケアマネジャーの役割は何か?暮らし、介護のことなど課題を抱えている時「人生の曲がり角」で関わりを持ちます。専門職として、その人を支えるための関係性を手繰り寄せて結ぶことが役割だと思います。
ケアマネジャーとして、どんなに小さな取り組みでも自分が身近な人を支えるためには何ができるかを考えることが、この但馬に住む一人一人が暮らし続けられる未来を創ることだと思います。
日本海新聞 2024年12月28日土曜日 018ページ
©新日本海新聞社



