
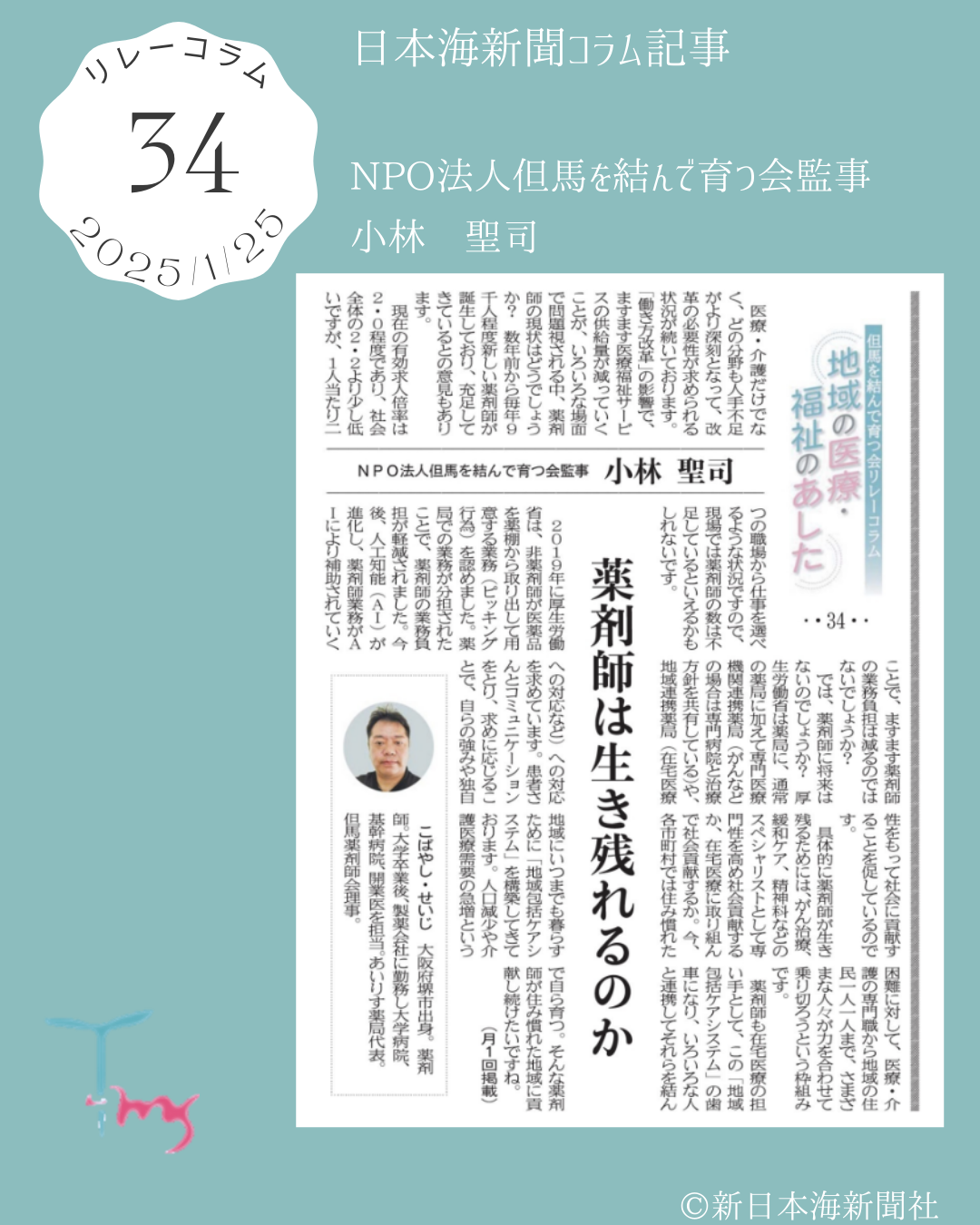
令和4年より、日本海新聞紙に‟但馬を結んで育つ会リレーコラム~地域の医療・福祉のあした~”が掲載されております。
令和7年1月は小林聖司監事の寄稿です。
『薬剤師は生き残れるのか』
医療・介護だけなく、どの分野も人手不足がより深刻となって、改革の必要性が求められる状況が続いております。「働き方改革」の影響で、ますます医療福祉サービスの供給量が減っていくことが、いろいろな場面で問題視される中、薬剤師の現状はどうでしょうか?数年前から毎年9千人程度新しい薬剤師が誕生しており、充足してきているとの意見もあります。
現在の有効求人倍率は2.0程度であり、社会全体の2.2より少し低いですが、1人当たり二つの職場から仕事を選べるような状況ですので、現場では薬剤師の数は不足しているといえるかもしれないです。
2019年に厚生労働省は、非薬剤師が医薬品を薬棚から取り出し用意する業務(ピッキング行為)を認めました。薬局での業務が分担されたことで、薬剤師の業務負担が軽減されました。今後、人口知能(AI)が進化し、薬剤師業務がAIにより補助されていくことで、ますます薬剤師の業務負担は減るのではないでしょうか?
では、薬剤師に将来はないのでしょうか?厚生労働省は薬局に、通常の薬局に加えて専門医療機関連携薬局(がんなどの場合は専門病院と治療方針を共有している)や、地域連携薬局(在宅医療への対応など)への対応を求めています。患者さんとコミュニケーションをとり、求めに応じることで、自らの強みや独自性をもって社会に貢献することを促しているのです。
具体的に薬剤師が生き残るためには、がん治療、緩和ケア、精神科などのスペシャリストとして専門性を高め社会貢献するか、在宅医療に取り組んで社会貢献するか。今、各市町村では住み慣れた地域にいつまでも暮らすために「地域包括ケアシステム」を構築してきております。人口減少や介護医療需要の急増という困難に対して、医療・介護の専門職から地域の住民一人一人まで、さまざまな人々が力を合わせて乗り切ろうという枠組みです。
薬剤師も在宅医療の担い手として、この「地域包括ケアシステム」の歯車になり、いろいろな人と連携してそれらを結んで自ら育つ。そんな薬剤師が住み慣れた地域に貢献し続けたいですね。
日本海新聞 2025年1月25日土曜日 020ページ
©新日本海新聞社



